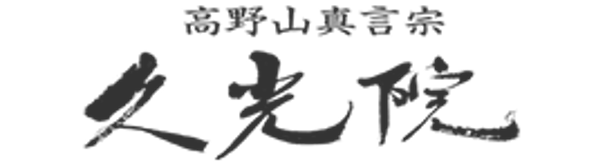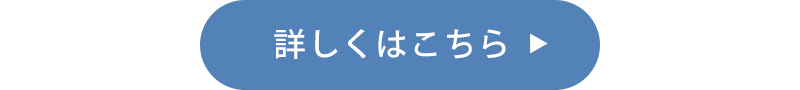おしらせ
催しのお知らせ
-Event News -


ページの更新
- Season News -

久光院のご紹介
- About -
アクセスマップ
- Access -
〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2-10-10
東急東横線「綱島駅」より徒歩6分
(駅から近く平坦な道のりです)
駐車場について
駐車場には限りがございます。近隣にはコインパーキングが多数ございますので、併せてご利用ください。
~鶴見川の流れと人に寄り沿いながら~